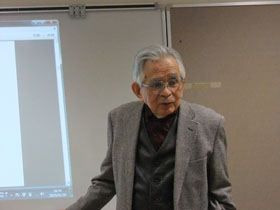
1月30日、東京・八丁堀のハイテクセンターでWebサイト完成記念として勉強会を行いました。
タイポロジの竹原悟代表が、「CD勉強会」は昭和40年ごろに千葉大学工業短期大学部の先生方と卒業生で始めた勉強会。当時は印刷について先生より(家業が印刷業であった)学生の方が詳しかったりして、ともに勉強していこうと始まった会だ。とルーツを紹介しました。そして「PIA資料から見た2014‐2015 米国印刷事情」と題し①PIAの出荷額予測は楽天的傾向にある、②PIAが財務指標とマネージメント項目との構造(多変量)解析に着手したようだ、③Demand Indexに見られるように市場の変化が激しい、④日本の印刷産業界にもチーフ・エコノミストとマーケッターを育てる組織が欲しい、などとまとめました。竹原氏の講演の資料はこちら
 また全国ぷらざ協議会の代表代行でCD勉強会顧問の五百旗頭忠男さんは「地域プラットフォームビジネスの今昔」と題し、無料宅配情報誌・月刊「ぷらざ」が佐賀市で誕生してから今日までの、地域生活情報誌を解説しました。地方では、チラシが最強の媒体であり、チラシは媒体対象者(消費者)、広告主、印刷会社の三方良しのフレームだったとのこと。そして、札幌の「ふりっぱー」、岐阜の「月刊ぷらざ」と宇都宮「トチペ」、帯広の「スロウ」、栃木の「栃ナビ!」、千葉・埼玉の「ちいき新聞」「チイコミ!」などの地域密着型生活情報紙誌のビジネス的な取り組みや特徴を紹介。注目すべきは栃ナビで、これは紙媒体でなく口コミサイトを15年かけて育成したもので、これ自体が立派なビジネスになっています。加えて、サイト自体から得られる消費者情報、お店情報をてこに創注印刷に結び付けています。全体の6割の売上が印刷売上であるが、これをSM74-8P(菊半裁8色反転機)+iGen4でこなしてます。創注印刷だからこそ、限定印刷機種でこなせる仕組みになっているのです。他方、紙媒体を継続する方策として、いかに紙のプラットフォームを補強し続けるか、チイコミを良き見本として模索を続けているとまとめました。
また全国ぷらざ協議会の代表代行でCD勉強会顧問の五百旗頭忠男さんは「地域プラットフォームビジネスの今昔」と題し、無料宅配情報誌・月刊「ぷらざ」が佐賀市で誕生してから今日までの、地域生活情報誌を解説しました。地方では、チラシが最強の媒体であり、チラシは媒体対象者(消費者)、広告主、印刷会社の三方良しのフレームだったとのこと。そして、札幌の「ふりっぱー」、岐阜の「月刊ぷらざ」と宇都宮「トチペ」、帯広の「スロウ」、栃木の「栃ナビ!」、千葉・埼玉の「ちいき新聞」「チイコミ!」などの地域密着型生活情報紙誌のビジネス的な取り組みや特徴を紹介。注目すべきは栃ナビで、これは紙媒体でなく口コミサイトを15年かけて育成したもので、これ自体が立派なビジネスになっています。加えて、サイト自体から得られる消費者情報、お店情報をてこに創注印刷に結び付けています。全体の6割の売上が印刷売上であるが、これをSM74-8P(菊半裁8色反転機)+iGen4でこなしてます。創注印刷だからこそ、限定印刷機種でこなせる仕組みになっているのです。他方、紙媒体を継続する方策として、いかに紙のプラットフォームを補強し続けるか、チイコミを良き見本として模索を続けているとまとめました。
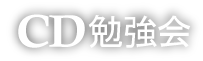

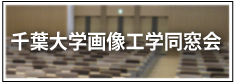
 トップページ
トップページ